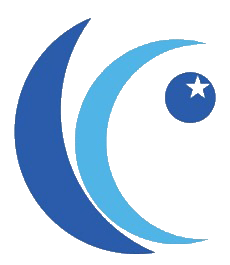高田(M2)のブラックAg膜に関する論文が公表されました
北見工大・北大・プラハ化技大(チェコ)と共同で進めた、高田くん(M2)の研究内容である、
真空蒸着法によるブラックAg膜の作製とその特性評価に関する論文が、
Appl. Phys. A誌に受理され、オンラインで公開されました。

https://link.springer.com/article/10.1007/s00339-024-07328-7
【解説】黒い銀!?光を吸収する新しい薄膜のつくり方
私たちがよく知る「銀(Ag)」は、ピカピカと光を反射する明るい金属です。でも、そんな銀が“真っ黒”になることがあると聞いたら驚くでしょうか?実は、銀をある条件で薄い膜として成長させると、光をほとんど反射せず、強く吸収する「黒い銀(Black Ag)」という材料ができます。この黒い銀は、太陽光を取り込む装置や、熱・光を測るセンサーなどに応用できる注目の素材です。
今回の研究では、銀を高温で蒸発させてガスの中に放出し、ガラス板などの上に薄膜として付着させる「熱蒸着」という方法を使って黒い銀の膜をつくりました。そのとき、蒸着する空間にアルゴンというガスを加えると、銀の粒がどのように集まるかが変わり、できる膜の構造も変化します。この「ガスの圧力」を変えることで、銀の膜がどれくらいスカスカになるか、またどれくらい光を吸収するかをコントロールできるのです。
同じ厚さでつくった膜の観察
まず、膜の厚さをすべて1マイクロメートル(1/1000ミリメートル)にそろえ、圧力だけを変えて作った銀の膜を比較しました。電子顕微鏡で観察すると、圧力が高いほど銀の粒がバラバラになってすき間が増え、スポンジのように“ふわふわ”した構造になることがわかりました。この構造によって光が膜の中に入り込んで吸収されやすくなり、表面は黒く見えます。
一方、圧力が低いと膜の下に“つるつる”した銀の層ができ、その部分は金属光沢のままでした。この違いが、膜の光の反射や吸収にも大きく影響します。
銀の量を同じにして比べると?
次に、使う銀の「量」をそろえて膜を作り、同じように観察しました。すると、圧力が高くなると膜がより厚くなる一方で、内部はスカスカの構造になっていきました。つまり、同じ量の銀でも“ふんわり積もる”ことで厚くなるというわけです。
光の吸収率を調べると、特に60Paや100Paといった高圧で作った膜では、可視光から赤外線まで幅広い光を90%近く吸収できることがわかりました。これは、太陽光を利用するエネルギー装置などにとって非常に有利な性質です。
銀の粒は空中で生まれていた?
これまで、金属の薄膜は「蒸発した原子が基板にくっついて成長する」と考えられてきました。でも今回の結果から、銀の原子が空中でガスとぶつかって小さな粒(ナノ粒子)になり、そのまま板の上に積もって膜を作っていた可能性が見えてきました。
この現象は「気相核生成」と呼ばれ、まるで空中で雪の粒ができて、地面に降り積もっていくようなイメージです。実際に観察された粒の大きさや結晶の情報から、この新しいメカニズムが支持されました。